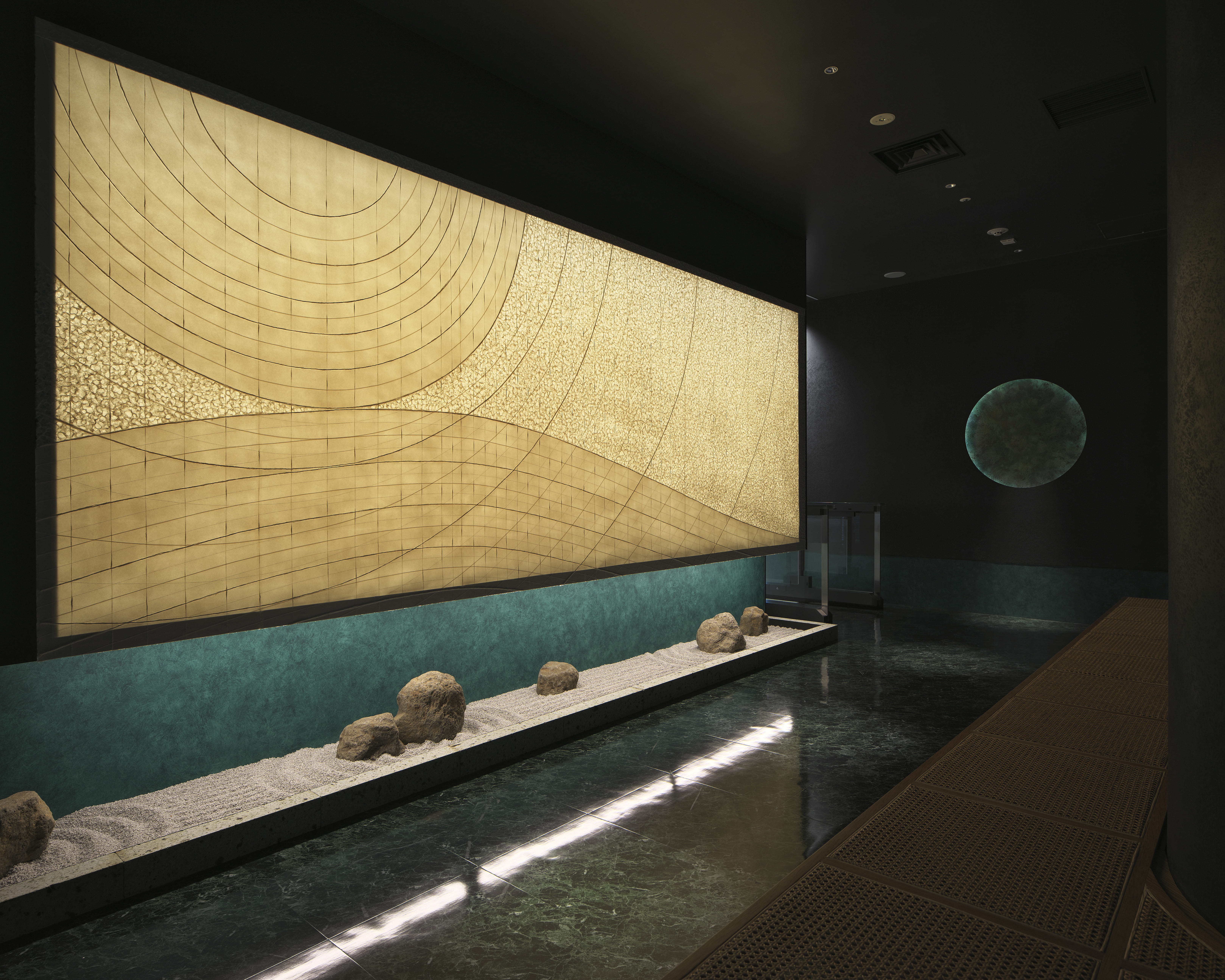こんにちは!第五話のテーマは「自然を感じる」です。
これまでウェルビーイングを高める方法として、「仕事を楽しむ」「気持ちの良い場所で働く」「身体で考える」と進めてきました。その延長にあるのが、自然とのつながりです。
1.自然に寄り添う、変化を楽しむ
まず、自然の中に身を置くことから始まります。そして、自然は人間がコントロールできるものではありません。てなずけようとしても、必ずしっぺ返しを食らいます。むしろ大切なのは、自然に「寄り添う」こと。つまり、自然の変化に合わせて自分の居方を調整することなのです。
暑い時には日陰を選び、寒い時には陽の光を求めて居場所を変える。パソコンに画面の映り込みがあれば、光の方向に合わせて座り直す。そうやって自然のリズムに追従することが、「自然に寄り添う」ということです。
私たちは、エアコンの効いた快適な空間に慣れすぎています。常に平均的な気温の中で過ごしていると、ちょっとした暑さや寒さをすぐに不快だと感じてしまう。でも実は、その「少しの我慢」の先に、自然ならではの喜びが待っています。汗ばんだ後に吹いてくる微風や、冷えた朝に差し込む陽射しは、自然がくれる何にも代えがたいご褒美なのです。

2. 自然がもたらす効果
自然を感じることは、ただ気持ちがいいだけではありません。実は、脳や体の仕組みにも深く関わっています。
たとえば、朝の光を浴びると“幸せホルモン”と呼ばれるセロトニンが分泌され、気分が安定し前向きになれます。森の中を歩くと深い呼吸とともにセロトニンの働きが高まり、心が落ち着いていくのを感じるでしょう。さらに、人と人が安心してつながるときに分泌されるオキシトシンも、自然の中で豊かになります。鳥の声や風の匂いに包まれると、不思議と安心感が広がり、誰かと共有するときには「つながっている」感覚が強まります。
自然は、セロトニンやオキシトシンといった“幸せの回路”をやさしく刺激しながら、心と体を同時に調律してくれる存在なのです。
3. 自然リテラシーを身につける
自然と共に過ごすには、ちょっとした「リテラシー」と意識の転換が必要です。季節や時間帯に応じて居場所を選ぶこと。光や風を読む感覚を取り戻すこと。多少の暑さや寒さを「耐える」のではなく「味わう」こと。
こうした自然リテラシーは、ほんの少しの我慢と工夫から育ちます。嫌だと避けるのではなく、変化を受け入れ楽しむ。そうすることで、不快は「自然との対話」に変わり、私たちの感覚は研ぎ澄まされていきます。
4. ソトワークへのつながり
自然に寄り添う姿勢は、そのまま働き方にも通じます。屋外で働く「ソトワーク」は、自然の変化に追従しながら働くスタイル。環境のリズムに合わせて居場所や姿勢を調整し、風や光を味わいながら仕事をする。
それは単に「外で働く」ことではなく、自然と対話するように仕事を進める実践です。自然のリズムと自分のリズムが共鳴したとき、心身は調律され、思考は柔らかくなり、創造性が高まるのです。

最後に
自然はてなずけられない存在です。しかし、人間はその変化に追従し、寄り添うことができる。暑さ寒さを受け入れ、変化のリズムを楽しむことが、働く人のウェルビーイングを深めてくれるのです。そして、それを日常に取り込むひとつの方法が「ソトワーク」。自然と共に働くことで、私たちは「生きている実感」を取り戻し、仕事と人生をより豊かにできると僕は思うのです。
さて、今回がウェルビーイングの最終回でしたが、一回増やして、ウェルビーイングの新たな展開として「ブエン・ビビール」の話をしたいと思います。と書いてはみたものの、勝手に増やして良いか分からないので、今回で終わるかもしれません。その場合は、ごめんなさい。そして、これまでお付き合い頂き、ありがとうございます。

合同会社Naka Lab. 代表 / 京都工芸繊維大学 名誉教授
知識情報社会における建築・都市をテーマに様々な活動と研究を行う。
特にこれからのワークプレイスに力を注いでおり、企業や協会と共同で次世代の働き方とワークプレイスを模索する活動を展開している。
また、新世代クリエイティブシティ研究センターセンター長(2018年まで)、日経ニューオフィス賞審査委員、国道交通省オフィスの知的生産性研究委員会建築空間部会主体研究WG主査、国道交通省次世代公共建築研究会新ワークプレイス研究部会長、長崎新県庁舎、兵庫県庁舎など多くの自治体のアドバイザーなどを務める。