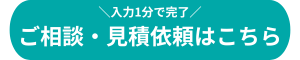総務省や厚生労働省をはじめ、行政もテレワーク・リモートワークの推進に力を入れています。テレワークやリモートワークの導入を検討しているものの、その違いを分かっていない人も多いのではないでしょうか。
この記事では、テレワークとリモートワークの違いと、テレワーク・リモートワークを導入するメリットを解説します。スムーズな導入には欠かせない準備についてもまとめているので、ぜひ参考にしてください。
目次
テレワークとリモートワークの違い

テレワークとリモートワークは、普段のオフィスとは違う場所で仕事をすることを指すという点において、ほぼ同義で使われていますが、厳密には言葉ができた時期やニュアンスがわずかに異なります。それぞれの定義や使われ方を詳しくみていきましょう。
1.テレワークとは?
「テレワーク」は政府や自治体で統一された呼び方です。総務省では、下記のようにテレワークを定義しています。
”ICT(情報通信技術)を利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方”
総務省『テレワークの意義・効果』
テレワークの歴史は1970 年代のアメリカではじまったといわれています。当時のアメリカは大気汚染が社会問題となっており、解決策の1つとしてテレワークが導入されました。日本では1980年頃より認知されるようになり、インターネットが急速に発達した1990年代後半から徐々に導入する企業が増えてきました。
2.リモートワークとは?
リモートワークは、近年広く浸透した呼び方。主に、民間企業やフリーランスで使用されています。
英語圏では普段のオフィスとは違う場所で仕事をする働き方のうち、普段からオフィスで勤務している場合は「テレワーク」、オフィス以外の場所で勤務している場合は「リモートワーク」と使い分けることがあります。オフィスに4日出社して自宅から1日だけ働くならテレワーク、1ヶ月のうち数日しか出社しないならリモートワークといったニュアンスです。
日本では、英語圏ほど明確に使い分けされておらず、遠隔(リモート)で働くことを総称してリモートワークが使われます。状況に応じて使い分けるとよいでしょう。
3.テレワークとその他の用語との違い
テレワーク・リモートワーク以外にも、在宅勤務・モバイルワーク・ノマドワークといった呼び方があります。
総務省のガイドラインでは、企業に勤務する被雇用者が行うテレワークには、「在宅勤務」「モバイルワーク」「施設利用型勤務」の3種類があるとされています。つまり、在宅勤務やモバイルワークはテレワークの形態の1つといえます。
ノマドワークは決まった勤務場所を持たず、遊牧民のように移動しながら働くスタイルです。ノマドワークは、IT企業やフリーランスで働く人に多い勤務形態で、こちらもテレワークの形態の1つとなります。
企業がテレワーク・リモートワークを導入するメリット

企業がテレワーク・リモートワークを導入するメリットには、次の4つがあります。
- コスト削減
- 雇用の確保
- 業務効率の改善
- 企業価値の向上
国が推進しているからテレワーク・リモートワークをはじめるのではなく、企業としてのメリットを理解したうえで導入することが大切です。
1.コスト削減
テレワーク・リモートワークを導入することで、従業員全員の座席を確保しておく必要がなくなり、オフィスの省スペース化が実現できます。オフィスがコンパクトになると、家賃や光熱費、交通費などのコスト削減につながります。
出社する従業員の数が減れば、交通費のカットが可能。テレワーク・リモートワークの広がりとともに、オフィス縮小を考える企業の割合は増加傾向にあります。さらに、フルリモートワークなら、賃料の高いエリアにオフィスを構える必要もなく、フレキシブルな働き方が可能となります。
2.雇用の確保
これまでの出社を前提とした働き方では、どれだけ優秀であっても通勤ができない人や通える距離に居住していない人は雇用できませんでした。一方、テレワーク・リモートワークの場合、住んでいる場所に関わらず働くことができるため、人材が確保しやすくなります。
テレワーク・リモートワークができる体制が整っていれば、育児・介護など家庭の事情で出社できない人の離職防止策としても効果的です。雇用形態に柔軟性を持たせることで、離職率を抑え、人材が定着しやすい環境を構築できるでしょう。
3.業務効率の改善
テレワーク・リモートワークを行うためには、システムの見直しが不可欠です。デジタル化が促進されることで、会社としても業務効率の改善が見込めます。
たとえば、テレワーク・リモートワークでは紙ではなくデータでのやりとりが基本です。社内文書を電子化し、ペーパーレス化を進めることで、生産性の向上が期待できます。
4.企業価値の向上
雇用形態が多様化するなかで、企業が選ばれる基準も変化しています。これまでは給与や待遇が重視される傾向でしたが、若い世代を中心に福利厚生や柔軟な働き方へのニーズが高まっています。
他社と差別化し、企業価値を向上させる施策としてもテレワーク・リモートワークは有効です。テレワーク・リモートワークを導入することで、従業員はプライベートの時間が確保しやすくなり、生活の質も向上するでしょう。
テレワーク・リモートワーク導入時に必要な準備

テレワーク・リモートワーク導入時に必要な準備を4つ紹介します。
- 作業環境の整備
- セキュリティの強化
- 制度や管理方法の見直し
- オフィスの再構築
テレワーク・リモートワークを導入することで、働き方は大きく変わります。導入後のトラブルを防ぐには、事前の準備が重要です。
1.作業環境の整備
作業環境の整備として、次の3つの施策を検討しましょう。
- ネットワーク環境の整備
- ICTツールの導入
- デスク・チェアの会社貸与
テレワーク・リモートワークでは、オフィス外からのアクセスが増加するため、負荷に耐えられるネットワーク環境の構築が必要です。加えて、勤怠管理・オンライン会議・コミュニケーションなどのICTツールがあると、テレワーク・リモートワーク業務が効率よく行えます。
また、家庭用の家具では正しい姿勢が保ちづらく、肩こりや腰痛といった身体の不調につながるため、テレワーク・リモートワーク用のデスクやチェアを会社で用意するのもおすすめです。
2.セキュリティの強化
会社PCの持ち出しや自宅PCの利用を前提とするテレワーク・リモートワークにおいて、セキュリティの強化は欠かせません。情報漏洩やウイルス感染などのリスクを減らすためには、セキュリティガイドラインやルールの策定が必要です。
「USBにはパスワードを設定する」「フリーWi-Fiにはアクセスしない」など、運用ルールを決めて従業員に周知しましょう。万が一、不正アクセスなどのセキュリティインシデントが発生した場合でも、データを暗号化しセキュリティソフトを入れておくことで、被害を最小限に抑えられる可能性があります。
3.制度や管理方法の見直し
テレワーク・リモートワークは従業員にもメリットの多い働き方ですが、在宅勤務に伴って電気代・水道代・通信費などの負担が増加します。企業には福利厚生制度を見直して、快適にテレワーク・リモートワークを行うための仕組みづくりが求められます。
たとえば、月額3,000円〜5,000円程度の在宅勤務手当を導入した会社も存在します。また、テレワーク・リモートワークに必要なデスクやチェアの購入費用の一部を補助する制度も人気です。テレワーク・リモートワークを導入するにあたっては、勤務管理制度の見直しも検討しましょう。メールやチャットで始業時間・終業時間を報告している会社は、オンラインで一元管理できる勤怠管理システムを導入すると業務が効率化できます。
4.オフィスの再構築
オフィスの再構築というと、オフィス環境の見直しをイメージするかもしれませんが、オフィスの移転も1つの方法です。
テレワーク・リモートワークを導入することで、オフィスの役割も変化します。これまでは固定された席で業務を行うのが一般的でしたが、テレワーク・リモートワークが普及した近年ではフリーアドレス制のようなスペースを有効活用できるレイアウトが注目されています。省スペース化を実現し、コンパクトなオフィスを再構築することで、コスト削減にもつながるでしょう。。
テレワーク導入時は「ソーシャルインテリア」でオフィス・作業環境の整備を

テレワークとリモートワークは、どちらも「オフィス以外の場所で働くこと」を意味します。テレワーク・リモートワークを導入することで、業務効率の改善や企業価値の向上も見込めるでしょう。
ソーシャルインテリアではオフィス構築の実績・ノウハウを生かして、それぞれの企業に最適な方法をご提案します。オフィス家具のサブスクもご用意しており、テレワーク・リモートワーク用のデスクやチェアをご用意することも可能です。オフィス移転のご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。