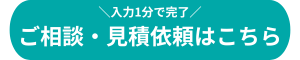働き方改革の取り組みのひとつとして、注目を集めているのが「ワーケーション」です。ワーケーションという言葉を聞いたことがあっても、具体的にどのような働き方をするのかイメージが湧かない方も多いのではないでしょうか。
この記事ではワーケーションの種類、注目されている理由、メリット・デメリットを解説します。ワーケーションの導入を考えている企業が知っておきたい課題と対策についてもまとめているので、ぜひ参考にしてください。
目次
ワーケーションとは?
ワーケーション(Workation)とは、「ワーク(Work)」と「バケーション(Vacation)」を組み合わせた造語です。テレワークなどを活用して、事務所や自宅以外の場所で仕事をしながら休暇やプライベートの時間を過ごす働き方を指します。
海外が発祥のワークスタイルであり、日本ではさほど普及していませんでしたが、観光庁がワーケーションを新たな旅のスタイルとして位置づけて、普及促進に力を入れるようになりました。その結果、近年では、仕事と休暇を両立させた新しい働き方として注目が高まっています。
これまでは、仕事と休暇を明確に線引きすることでワークライフバランスの実現を目指してきましたが、ワーケーションは「休暇を楽しみながら仕事をする」といった新たな選択肢になるものです。
ブレジャーの違い
ワーケーションと似た用語に「ブレジャー」があります。ブレジャー(Bleisure)とは、「ビジネス(Business)」と「レジャー(Lesure)」を組み合わせた造語で、出張業務の前後に有給休暇を組み合わせる働き方のこと。
ブレジャーは、仕事に比重を置いた業務型のスタイルですが、有給休暇を取得した日は近隣エリアの周遊など自由に過ごすことが可能です。また、出張の隙間時間や仕事の前後にレジャーを楽しむ方法も、ブレジャーに該当します。
ワーケーションは旅行先や帰省先への費用は従業員の自己負担となるケースが多い一方で、ブレジャーは業務を遂行するうえで必要な経費であれば会社負担となるのが相違点です。
ワーケーションの種類
ワーケーションは、主体となる時間の過ごし方や目的などによってさまざまな種類に分けられます。ここでは、観光庁が提唱するワーケーションの5つのタイプについて解説します。
1.休暇型ワーケーション
休暇型ワーケーションとは、休暇として観光を楽しみつつ、合間に普段の仕事を行うスタイルです。観光地やリゾート地などに滞在し、必要なときだけリモートワークを行うという柔軟な働き方を通して、ライフワークバランスの実現やモチベーション向上につながります。
また、これまで「溜まった業務や打ち合わせがあって休みが取れない」といった課題を抱えがちであった企業でも、長期休暇の取得促進に役立つ可能性があります。
福利厚生型
福利厚生型ワーケーションは、企業の福利厚生としてワーケーションを実施するスタイルです。社員の健康増進や学び直し、有給休暇の取得推進などを目的として導入する企業も見られます。
旅行先や帰省先からのテレワークが可能であるため、有給休暇の取得促進や従業員のモチベーション向上、リフレッシュ効果などが期待できます。主体となる時間は休暇であるため、移動や宿泊などの費用は原則として個人負担です。
2.業務型ワーケーション
業務型ワーケーションは、仕事をメインとし、業務時間の前後や合間、定時後に休暇を楽しむスタイルです。近年は企業だけでなく、自治体や宿泊施設が企画する独自の業務型ワーケーションも増加傾向にあります。
受け入れ地域や企業によって、地域課題解決型・合宿型・サテライトオフィス型などの種類に分けられるのが特徴です。
地域課題解決型
地域課題解決型ワーケーションは、地域の課題解決を目的とし、ワーケーション先でさまざまな活動を行う形式です。企業が指定した地域に赴き、研修活動や新規事業の創出、社会貢献を目的としたボランティアや交流などを通して、地域課題の解消を目指します。
活動内容やタイムテーブルなどが決まっており、休暇型よりは制約が付いています。また、地元の人を含む交流が前提であるため、ゲストハウスやコワーキングスペースなどを利用します。なお、ワーケーションに積極的な自治体からサポートを受けられる場合もあります。
合宿型
合宿型ワーケーションは、宿泊を伴う業務やさまざまな取り組みを行うスタイルです。通常の職場から離れたリゾート地や旅館、保養所などで各種研修やワークショップを実施します。
社内のコミュニケーション活性化やアイデア創出、チームビルディングなど集団で行う取り組みを通して、部署やチーム内での関係強化やエンゲージメントの向上といった効果が期待できます。プロジェクトの立ち上げ時や新人研修などにも向いています。
サテライトオフィス型
サテライトオフィス型のワーケーションは、日頃使っているオフィスとは異なる場所でテレワークを行うスタイルです。企業が開設しているサテライトオフィスの他、一般的なシェアオフィスやコワーキングスペースなどを利用して業務を行います。
また、必要な期間や席数に応じて、観光地のホテル会場を利用するケースも見られます。仕事場所を選ぶことでリフレッシュやイノベーションの創出などのメリットが見込めるでしょう。
ワーケーションが注目されている背景
日本国内でワーケーションが注目されている背景には、「働き方改革の広がり」と「新型コロナウイルス感染症の流行」があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.働き方改革の広がり
日本では2018年に働き方改革関連法が成立し、2019年4月から順次施行されています。働き方改革の広がりと共に、企業には多様な働き方への対応が求められるようになりました。
とくに、年次有給休暇の取得が義務化されたことは、大きな変化です。従業員が長期休暇を取りやすい状況を確立するためにも、ワーケーションが効果的だと考えられています。
2.新型コロナウイルス感染症の流行
2019年12月に発生し、世界的な大流行を引き起こした新型コロナウイルス感染症もワーケーションと深い関わりがあります。緊急事態宣言が出されたことにより、テレワークが急速に普及し、出社しなくても働ける環境が整備されていきました。
一方、外出自粛やインバウンド減少により大きな打撃を受けた観光業界は、「コロナ禍ならではのビジネス」に取り組むようになります。自宅での働きづらさを感じている人に、「ホテルでのテレワーク」「地方拠点の設置」などを提案した結果、ワーケーションという働き方が徐々に認知されるようになりました。
3.観光庁や自治体の促進
観光庁や自治体がワーケーションの推進を支援している点も背景にあります。地域の課題解消や観光促進といった視点から、国や自治体がワーケーションの促進を支援したことで、一般への認知が広がりました。
観光庁では、モデル企業や地域の公募、宿泊事業者への補助金制度の創設、企業への情報提供など、さまざまな活動を通してワーケーションの普及や定着を支援しています。ほかにも、長野県や北海道、沖縄県などの自治体が独自で「ワーケーション自治体協議会」を発足し、ワーケーションの普及に向けた体験会やオンラインイベントを開催しているのも大きな動きといえます。
ワーケーションを導入する企業のメリット
ワーケーションを導入することで、従業員と企業それぞれに多くのメリットが期待できます。ここでは、企業がワーケーションの導入によって期待できるメリットについて解説します。
年次有給休暇の取得促進
ワーケーションを導入することで、有給休暇の取得促進につながります。日本人に見られやすい「休まない性質」により、有給休暇を取得する人が少ない傾向があります。
エクスペディアが実施した有給休暇の取得に関する国際調査(2022年)によると、対象となった世界16地域のうち、日本の有休取得率はワースト2位の60%でした。この原因として、「同僚や上司が働いていて自分だけ休むことに後ろめたさを感じる」といったケースが考えられます。
また、「やむを得ない事情以外で休むことで、仕事をする気がないと思われる」といった不安を抱える人もいるでしょう。長期休暇や有給休暇の間に仕事が溜まり、休み明けの負担となることを懸念してなかなか休めないことも考えられます。
ワーケーションを活用することで、休暇を取りながら仕事をするという新しい選択肢が生まれ、有給休暇取得のハードルが下がる可能性があります。
従業員エンゲージメントの向上
ワーケーション導入は、従業員満足度やエンゲージメントの向上につながります。ワーケーションにより休暇の時間が増えることで、ストレス軽減やリフレッシュ効果、仕事に対するモチベーションの向上といった効果が期待できます。
また、勤務場所や時間の制限が撤廃され、働き方の自由度が増すことによって、社員は「会社から信用されている」という自信を得られます。結果的に従業員の会社に対するエンゲージメントが高まり、組織力アップや業績向上にも役立つでしょう。
企業価値の向上
ワーケーションを通して、新たな事業アイデアやイノベーションの創出が促進され、企業価値の向上につながります。ワーケーションで自然の中やリゾートなど非日常の環境で過ごすことで、新しい発想やアイディアが生まれ、イノベーションが促される可能性もあるでしょう。
また、地方創生に向けた活動は企業のPRやブランディングとしても効果的で、人材獲得の点でも効果が期待できます。多様な働き方を積極的に取り入れていることのアピールにもなるため、離職率の低下に結びつくでしょう。
ワーケーションを導入するデメリットと対策
ワーケーションを導入することで、企業には以下のデメリットがあります。
- 労務管理の煩雑化
- 環境整備のためのコスト増大
働き方が多様化することで、労務管理の負担が増えます。また、新しい環境に対応するための設備導入などで、コストの増大も予想されます。対策としては、次の3点が有効です。
- 勤怠管理システムの整備
- 人事評価システムの再構築
- セキュリティ対策の強化
柔軟な働き方ができるワーケーションでは、「仕事をしている時間」「仕事をしていない時間」が曖昧になりがちです。パソコンを起動している時間と連動した勤怠管理を行うなど、業務内容に合わせたシステムを整備しましょう。
また、勤務態度の確認の代わりに業績や成果の評価割合を高めるなど、人事評価システムの再構築も必要です。セキュリティ対策としては、新しくツールを導入する以外に、社内ルールの周知も重要です。「フリーWi-Fiにはアクセスしない」「紛失時は速やかに情報システム室に報告する」など、ルールを周知するだけでもセキュリティリスクは軽減できます。
ワーケーションのよくある質問
ワーケーションに対して良いイメージを持っていない人のなかには、働き方を誤解しているケースもあります。ここでは、ワーケーションに関する誤解を2つ紹介します。
1.ワーケーションは強制?
ワーケーションは従業員が自主的にとるもので、企業が利用を強要するものではありません。「休暇中は仕事のことを考えず、ゆっくりと過ごしたい」という人もいるため、数値目標などは定めず、休み方の選択肢のひとつとして提示する程度に留めます。
強要したところで企業にとってプラスにならないので、取得は個人の自由であることを従業員にも徹底して伝えましょう。
2.仕事とプライベートを分けることができない?
ワーケーションで仕事とプライベートを分けることは可能ですが、明確に分けられる仕組みや工夫が必要でしょう。ワーケーションは「休みの日に仕事をしなればならない仕組み」ではなく、観光地や自然の中で休暇を楽しみながら自分のペースで働くことを狙いとしています。
「仕事とプライベートが曖昧でも構わない」「リラックスした休暇中のほうがアイデアが湧く」といった人は、ワーケーションが向いています。一方で、「仕事とプライベートをはっきり分けた方が効率良く過ごせる」という場合は、ワーケーションを利用する必要はないでしょう。
ワーケーション促進にはサテライトオフィス創設もおすすめ
ワーケーションを浸透させるために、サテライトオフィスの創設・利用もおすすめです。サテライトオフィスとは、事務所とは別の場所に設置されたオフィスのことです。
普段使用するオフィス以外の場所から、テレワークやクラウドシステムを活用して業務ができるため、リフレッシュ効果や革新的なアイデアの創出といった効果が期待できます。郊外にあるサテライトオフィスの場合、近隣に住む社員の通勤時間を短縮でき、ストレス軽減やプライベートの充実にも貢献します。
サテライトオフィスの用途や目的に応じて、自社オフィスとは違ったデザインやオフィス家具を取り入れることで、ワーケーションの効果を高められるでしょう。
ワーケーションの魅力を生かして企業導入を検討してみよう
ワーケーションは、仕事と休暇を組み合わせるワークスタイルです。柔軟な働き方の実現やイノベーション創出といったさまざまなメリットが期待できます。観光庁や各自治体も積極的に支援を行っており、自社に合ったタイプのワーケーションの導入をこの機会に検討してみてはいかがでしょうか。
サテライトオフィスを構築する際には、オフィス家具のレンタルがおすすめです。ソーシャルインテリアでは、オフィス家具のサブスクリプションサービスを提供しており、オフィス移転やデザイン構築と合わせたご相談いただけます。まずは下記よりお気軽にお問い合わせください。